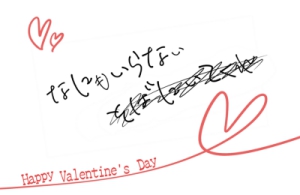ディヴェルティメント・バレンタイン
Side Cloud
一応、用意はした。
したものの、次はどうすればいいんだ。
ティファに付き添ってもらって、店に入って一番最初に目についたものをすぐ手に取った。そんなに慌てなくても、と焦るティファの買い物に付き添うふり をしながら辺りを見回し、店員と目が合いそうになった瞬間、足元に視線を落とす。俺の気持ちなんて全く知らないであろう女性店員はにこやかにこちらを眺め続けたまま、姿勢よく立っている。きっと男である俺がチョコレートを買うだなんて、思いもしないだろう。
「クラウドから渡してみたら?」
「何を?」
「バレンタイン。ほら、ザックス……帰ってきたんだし」
目を細めて笑うティファからも、視線を逸らす。
ザックスが突然俺の前に現れ、わけがわからないまま力を貸せと言われた。俺があの時葬ったはずのセフィロスを二人揃ってもう一度追い返してから、もうすぐ一年。新しい街エッジで、なんでも屋としての生業も軌道に乗り始めているところだ。
「バレンタイン……」
「ほら、クラウド、そういう物を渡した事ないでしょ? たまにはいいんじゃないかな」
「……」
言葉の意味自体は理解するが、その提案には素直に納得出来なかった。そんな甘酸っぱいイベントなんて、子どもの頃から俺には全く持って縁のない物だ。それこそ、ティファから貰えるかもしれないとすら、思わなかった程には。
「クラウド、どれにするか決まった?」
「いや、俺は……」
「買い辛いなら私が一緒にお会計するから、ね」
買い物カゴに山盛りの箱を入れたティファがレジへと向かって行く。慌ててその後ろを追い、手に持っていたそれをそのカゴに放り込む。店員と会話しながら支払いを済ませるその背中が、なぜだか普段の数倍頼もしく見えた。
「おかえりクラウド、荷物持ちごくろーさん」
「ああ、うん」
明日の配達準備に追われているザックスと言葉を交わす。黒髪のツンツン頭はいつもと同じように声を上げ、特に普段と変わりはない。一方の俺はというと、どことなく浮ついた気持ちで返事を返すしかなかった。当たり前の会話なはずなのに、どこか落ち着かない。手元の袋の一番底に隠れているそいつの事が、気になって仕方がない。
「明日は忙しいぜ、なんたってバレンタインだから」
「ああ、うん」
「おこぼれに預かれたらいいなー。チョコ食いまくろうぜ」 「……うん」
俺の気なんて当然知る由もないザックスは、能天気なセリフを吐いてカームへの荷物が詰め込まれた段ボールに封をする。ミニマムが荷物にも効いたらいいのにな、なんてバカげた事を呟いて、倉庫へと向かっていった。
「はぁ」
ティファに言われるがまま勢いで買ってしまったチョコレートをそっと手に取り、眺めてみる。白い箱にピンク色のハートがでかでかと描かれた代物だ。慌てて手に取ったとはいえ、よりによってこんなパッケージデザインの物を買ってしまったのは大失敗だったかもしれない。特設の大規模催事場だ、もう少し落ち着いたデザインの物だって、沢山あったはずなのに。
「ところでさぁクラウド!」
「うわっ!」
勢いよく開け放たれた入り口のドアから、大きな声と共にザックスが戻って来た。慌ててチョコを体の後ろに隠し、一歩後ずさる。ばっちり目があってしまった俺の顔は、いつも通りで――いられる、はずがない。
「ん、なんか隠した?」
「な、なにもない」
「いやいや、怪しいなぁ……あ、さてはへそくりだろ!」
「あ、あんたには……関係ない物だ」
しばらくにらみ合った後軽やかに笑ったザックスは、それ以上言葉を発さないまま忘れ物を手に取り、再度荷物を運びに行った。ザックスの察しの良さには幾度となく助けられてきたけれど、時々、辟易することもある。元ソルジャーの勘だよと笑って終わる事がほとんどだが、良くも 悪くも隠し事は出来ない相手だ。
――決して用意したものを渡したくないわけじゃない。だけど――
いつも通りに朗らかに俺に話しかけるザックスの目が俺の視線とかち合う瞬間、顔がほころぶ感覚は嬉しい。視界に存在しているという安堵感に、こっちだって何度も奥歯を噛みしめている。
それでも頭の中は隠したチョコレートの事でいっぱいで、どこかザックスの声にのめりこめないまま、もう一度その箱をジッと見つめる事しか出来なかった。
Side Zack ――チョコだ。 あれは絶対チョコだ。 俺の勘がそう言ってるんだ、絶対に間違いない。
「だとしても、なんで隠す必要が……」
愛の告白なんて物がしたためられた手紙でもついてたんだろうか。
あんなに赤い顔をして大慌てで隠さなきゃいけないような物、だったんだろうか。
「もしかして、なんか、いい感じになってる女の子がいるとか……!」
もしそうだったら、俺的には割とゆゆしきじたい、だ。一応俺とクラウドは一応、いちおう、そういう関係、で、そういう仲、だ。普段特に言葉にして口に出したり、あからさまな態度で街中を歩くことなんてほとんどないけれど(だってクラウドすっげえ嫌がるし、俺自身もそういうのは趣味じゃない)、そんな事をいちいち口に出さずとも、お互い同じ気持ちだと思ってた。 思い込んでいたのは、俺だけ? それとも、あいつの気持ちが俺から離れた?
「いや、いやいや、そんな事はありえない……よ、な?」
ブツブツと湧いて出る独り言と一緒に、時計を見た瞬間立ち上がる。明日、カームへの配達ついでにと頼まれていた荷物を、ティファの店まで引き取りに行かなきゃいけなかった。
「ザックス、ありがとう。これお願いね」
「ああ、任せといて。安全かつ迅速にお届けするぜ」
「よろしく。そういえば……クラウド、何か言ってた?」
「えっ」
ティファの口から出る聞き馴染んだ名前に一瞬、心臓が跳ねる。
何か言ってたかと言われたって、何か言われるどころか、隠されてるんだけど。
「……あ、ごめん、なんでもない」
「……」
笑って誤魔化し、配達お願いね、と背中を返す。店の準備に取り掛かる細腕を掴んで問い正しそうになったけれど、さすがにそんなダサい事はしたくなかった。 とりあえずその場を後にして、手持ち無沙汰に街中をブラつく事にする。
ミッドガルを模して造られたエッジは、完璧とまではいかずとも確かにどこか懐かしさを覚える街だ。大通りから一本逸れた奥にある公園の遊具も、時々見るだけで頬が緩む。
「ふあー……どーすっかなぁ……」
さすがに大の男が滑り台の上に三角座りするわけにもいかず、誰もいないベンチに座り込んだ。明日の配達準備の最終確認がまだ残っていることは勿論忘れちゃいないけれど、なんとなく、クラウドのいるアパートへまっすぐ帰る気がしなかった。 両腕を全力で広げ、背もたれに寄り掛かる。
自然と頭は空を向き、それからゆっくり重力に従って、世界がひっくり返った。
「もしもーし」
「……んぁ、エアリスだ」
天地がひっくり返った俺の視界に急に現れたエアリスが、隣に置いたワゴンから手を離して隣に座る。いつもと同じようにふんわりと花の匂いがして、少し心が落ち着いた。
「仕事サボってどうしたの?」
「聞いてくれよ! クラウドが……あー、いや」
話しかけて、口を噤む。首を傾げたエアリスに愛想笑いを返すと、何かを思いついたように手を叩いてワゴンに手を突っ込んだ。
「これ、あげる」
「いやいや、売り物だろ? 財布、いっぱいになったのかよ」
「ご心配なく。ザックスよりは、いっぱい、だよ!」
最後の一つをどうしようか悩んでいた、とエアリスは笑う。明日のバレンタインが売り時だからといつもよりは少なく用意していたそうだ。いつのまにやら 商魂もほんの少しだけ逞しくなったエアリスが、順調に売れた花の最後のひとつを俺に渡して立ち上がる。
「ザックス。明日はバレンタイン、だよ」
「チョコくれんの?」
「だから、お花! あげたでしょ」
花じゃ腹は膨れないよ、と言いかけてやめる。相変わらず小首をかしげた割に、深く聞いてこようとしないエアリスの態度はある意味ありがたい。
「ケンカ……じゃ、なさそうだね」
「ぜーんぜん、そんなんじゃないよ」
「なら、大丈夫。なにも心配ない、ね」
じゃあまたね、とその場を後にするエアリスに片手を上げ、見送った。
ひんやりした風に揺れる花と一緒に、クラウドの待つアパートの方に視線を移す。次から次へと建てられていく高層ビルの向こう側にあるアパートで、クラウドはきっと今もあのチョコを隠しているに違いない。
「っあー! もう! 俺らしくねえ! 直接聞きゃいいだけじゃん!」
意を決して立ち上がる。陽が落ちて一層寒くなったエッジの大通りを緩やかに駆け抜ける。そのほんの一瞬の間にも、クラウドの慌てた顔が何度も頭に浮かんで消えてを繰り返した。
Side Cloud
好きだとか、愛してるだとか、そんな事をいちいち口にするような仲じゃない。そんな言葉で片づけられるような間柄なら、こんなに悩むことなんてなかっただろう。出会って、ほんの少しだけ一緒に居て、それから永遠にもう会えないと思っていた相手と今こうして一緒に生活が出来ている奇跡。この感情間隔に、名前なんて、付けられない。
仮に渡すとして、だ。どうやって渡す?
食事の後に立ち上がって部屋に取りに戻るか?
ザックスが一番に気付くよう、これ見よがしにテーブルに置いておくか?
どちらにしたって白々しい。例えばマリンがそう言う風にしてくれれば、それはかわいらしいはずだ。きっとザックスも喜ぶだろう。だけど、渡すのは俺だ。用意したのも、俺だ。俺みたいなかわいげも何もない男が、あいつに一体どういうシチュエーションでこれを手渡せと。
――そもそも贈り物なんて物がもう、ガラじゃない。 俺が適当に選んで手渡した所で、そんなの。
「……やっぱりやめよう」
催事場のワゴンに大量に並べられていた時点で、かわいらしいリボンの巻かれた箱だった。赤いそれの端っこを一思いに引っ張り解くと、するするとベッド の上に落ちる。白く、所々にキラキラと光る不思議なデザインの紙箱の底には、店員が気を利かせてサービスしてくれたメッセージカードまでが揃えて入っ ていた。
何もかもがあまりにも自分には向いていないデザインである事に、ついに苦笑いまで漏れてきてしまう。ベッドの上に座ってそれをひたすら眺めていた体を起こし、デスクの上のペンをとる。
例えば。どうしても何かを書かないといけないとしたら。 今の俺なら、何と書くんだろう。
――どうせ捨ててしまうものだ、何を書いたって許される。本人の目にさえ触れなければ、こちらにとってはノーダメージだ。ペンを握り、数秒悩み、頭にふと浮かんだ言葉を書きこんでみる。
「こ、こんなの絶対に見られたくない……っ」
目頭が突然熱くなり、顔にその熱が伝播する。得体のしれない羞恥心に圧倒された俺の手が、物凄い速さでカードを封筒に押し込んだ。
とりあえず、今から証拠の隠滅をしなければいけない。今のうちに自分で食べてしまえば多分バレないだろう。空箱は自分で持ち歩いて、明日の配達の際に適当な所でファイガをかければ問題ないと自分自身に言い聞かせ、箱の底へと挟み込んだ。強火で燃やせば、灰もきっと、残らない。
箱の中に点々と入ったチョコレートは丸や四角の形を模していて、見ているだけでも十分甘さが伝わって来る。元々そんなに甘い物が嫌いなわけではないけ れど、流石にこれを一度に食べきるのは少し気合が必要だ。
一つ、指でつまむ。口の中に放り込んだ瞬間、舌先の熱に素直にとろけ落ちるビタースイートを転がしながら、次の獲物を拾い上げる。一つめが溶けてなくなり、喉の奥に消えて行くのと同時に、新たに口に押し込んだ。
「……」
こんなものを渡す気なんて全くなかった。ティファに一言言われて慌てて手に取ったチョコなんて渡した所できっと、ザックスがびっくりするだけだろう。愛想も良く、人付き合いも俺と違ってうまい奴だ。配達先の得意先からいくつもらって帰って来るかなんて、想像もつかない。
「甘い……」
本当に渡したくなかったのかと言われれば、決してそうではない。 だけど、渡したところできっと。
「……」
飲み下すのがだんだん辛くなってきたのは、数のせいじゃない。甘さだけのせいでもない。込み上げる自分の感情を喉の奥から吐き出したい衝動に、蓋をしたいだけなのに。
「あと半ぶ……っ!」
突然背後から、騒々しい音が聞こえた。乱暴に開いたドアが閉まり、ごつごつとなる足音が物凄い速さでこちらに近づいて来る――まずい、ザックスだ。
慌ててベッドの上に散らばった包装紙やチョコの箱をかき集める。蓋の上に重ねていた本体を引き抜こうとしてもうまく手が動かない。 急げ、速く片づけろ、じゃないとザックスに――
「クラウドぉ! そのチョコ誰から……」
「あああ違う! これは!」
「ああああ食ってる! うわーっなんだよ! 俺に隠れて食べなきゃいけないような相手からの物なのかよ!」
振り返った先には物凄い勢いで部屋のドアをぶち抜いたザックスが、顔面蒼白で立っている。軽く上がった息を整えながら立ち尽くすその口からこぼれた言葉の所々に少し違和感を抱きながらも、必死で言い訳を考えた。
「ちが、これは……っ」
「お客さんからなら半分こって約束だろ! 俺に分けてもらえない相手って!」
「だから、これは……!」
「いい、いいんだよ言い訳しなくて! ただ隠し事しないでくれってだけで!」
「違うって言ってるだろ!」
慌てて弁解しようとすればするほど、ザックスは俺の話を聞いてくれなくなっていく。半泣きの顔で抗議してくる相棒への誤魔化しがきかなくなっていく危機感。それでもなんとかしたかったけれど、多分、これはかなり俺の分が悪い。明らかに劣勢だ。
「誰から……」
「だから、誰でもないんだって言ってるだろ!」
「……えっ」
秒で涙をひっこめたザックスの目が開かれる。喉の奥に押し込んで、チョコレートの海に沈めてしまおうとしていた言葉が、ついにあふれ出る。
「俺が、自分で……買った」
「クラウドが? クラウドに?」
「……は?」
――もしかしてこいつ。
「そうじゃない……ティファの買い出しに付き添って、そこで」
「……自分チョコってやつ?」
俺が思っているより、ニブいのか?
「……あんたまさか、知らないはずがないよな……? バレンタインの事」
「え……あー……」
白々しく頬を指で掻き、ぶち抜かれた扉を応急処置しながらザックスは口を噤んだ。俺にももう、それ以上言葉で説明する気力は残っていない。適当にガムテープやなんやで扉を修復したザックスが、ベッドの淵に腰かけた。
「もしかして、さ……俺に用意してくれた……?」
指先がひくりと動く。覗き込まれた自分の表情を読み取られたくなくて、思わず顔を背けてしまう。
「ええっ、じゃあなんで渡してくれないんだよ!」
「ストレートに聞いて来ないでくれ……」
ザックスはいつもこうだ。俺が言いたい事、伝えたい事、抱え込んでいる割に伝えたくて仕方がない内面思考に簡単に滑り込んで来る。察してほしいわけではないけれど、俺が一番話しやすい方法を知った上で、甘やかす。
恐ろしく穏やかな声で問いかけられ、なんとなく指先で撫でた口の中。残る甘さが、薄らいでいく。
「あーあ、安心した」
「……疑いすぎだ。あと、慌てすぎ」
「そりゃ不安にもなるだろ、俺だって神様じゃないんだし。お前の考える事、何もかも全部透けて見えてるわけないんだから」
眉間に寄せた皺が元に戻らない俺の額をこすり上げる親指に、思わず脱力する。両手に抱え込んだチョコの箱をそっと取り上げたザックスが、残り少なくなった粒を手に取った。
「……もらっていい?」
耳元に響く掠れた声に、ぞわりと背筋に寒気が走る。直接的な言葉なんて何一つ交わしていないけれど、それでも本能的にその声が求めている物を察知する。
――没頭、という言葉が頭をよぎる。振り払う事をあっさり放棄しながら声も出さずに頷くと、拾い上げた一粒を俺の口に放り込み、唇に触れられた。
嫌気がさすほど甘ったるい口の中に、ザックスの舌先が触れる。受け入れて同じように絡め、その感覚に集中した。
触れ合った瞬間閉じた瞼に流れ込む景色 は全部遮断されて、温かい手のひらから両腕に伝わる熱が心地いい。微かに力を込められた指先に添うように手を這わせ、剥がす。指と指を絡めながらうっすら開けた目に、ザックスの睫毛が映る。 ゆっくりと開かれた青い瞳に吸い込まれるならきっと、今しかない。
「甘いな」
「ああ」
腰に回された両腕に力が籠る。ほんの少し窮屈なその感覚に再び目を閉じて、それから同じように腕を回す。
「こんな甘いの一人で全部食べるなんて、ずるいぞクラウド」
肩に置かれた顎元から漏れる声が耳に響く。どんよりと体がベッドに沈んで行く感覚に抵抗する気がなくなっていく。もう一度重なった唇にやんわり噛みつ くと、くぐもった笑い声が漏れた。
「こら」
「ふふ」
言葉少なに肌に触れ、ざわついていた心が凪ぐ。
眠くなんてないのに、瞼が重くて開けられない。
これ見よがしに舌を出せば、それに応じて俺に抱き着いてくれる。絡まった舌からほのかに伝わる甘さを誤魔化したくなりザックスの髪を指で梳くと、くすぐったそうに頭を振って唇を離す。ため込んだ息をほぼ同時に二人で吐き出して、首に回した腕はそのままベッドに倒れ込む。冬のよく晴れた空と同じ色の瞳が、俺の体に影を作った。
「なんつーか……俺、クラウドのそういうとこ、好き」
「はぁ?」
何でもない、と頬にかかった髪を撫でて払い、頬にキスを落とされる。ベッドの上に倒れ込んだ俺のファスナーに再度手をかけて、ゆっくりと滑り降ろされ た。
ザックスの手が柔らかく腹を撫でる。ゾワゾワと上がる心地よさに、思わず息を吐く。額に一つ降ったキスを受け入れて、両の手でその頬を挟みこむ。
「むぅ」
気の抜けた声に笑いで返し、抱き寄せる。綺麗に整えられた髪をぐしゃぐしゃに乱せば、抗議の声が上がる。それすらただいとおしく、腕から力が抜けてい く。
かさりと耳元で音が鳴り視線をそちらに向けると、俺が一人で食べ切ろうとしていたチョコの箱がその存在を主張している音だった。顔のすぐ側に置いてある事実になんとなく落ち着かず、少し遠ざける。
「ちょーだい」
「……ん」
無理矢理捻った手でつまみ、口に放り込む。ぽこりと膨らんだザックスの頬を指でつつくと、小さく音を立てて、短いキスが降ってきた。
「こら、行儀悪いだろ」
「ベッドの上で隠れ食ってたやつに言われたくありませーん」
「……確かに」
額をくっつけて、笑う。
一人で勝手に渡さないと決めて、一人で勝手に悲しい気持ちになっていた。そんな状態でチョコを口にしていたついさっきまでの感情が、どんどん薄らいでいく。喉元に滑り落ちたザックスの唇がくすぐったくて、自然と漏れる声。鎖骨のあたりを舐められれば、ひくりと体が疼き出す。
「ザックス、そこは、ダメだ」
「ダメ?」
「……っ、もう少し下なら……っ」
「んー」
いつも必ずどこかに痕を残そうとする大型犬のような相棒。手綱を手放してしまえば最後、どこに何をされるかわからない。
「ふ、ぁっ」
「ここは?」
胸元のぷくりを甘噛みされ、声が出る。反射的に手の甲で口元を押さえると、ほんの少し意地の悪い顔をしたザックスと目が合った。
――ああ、火がついた。
決して柔らかくなんてない、曲がりなりにも鍛え続けてきた体だ。肌だって、美しい言葉で褒めそやされるような代物じゃない。それでもザックスの指先に 撫でられれば――自分でも驚くほど、熱を持つ。
「クラウド、さわっていい?」
「……ああ」
「俺もさわって」
言われるがままそろそろと手を伸ばし、ザックス自身に触れる。ゆるゆると勃ち上がり始めているそこをそっと掴み、さする。ふぅ、と息を吐いたその顔を、ただ見上げた。
「はぁ……っ」
「ん……気持ちいい」
だんだん上がってくる息に合わせて、自分自身から先走りが伝い出す。指先でくりくりといじられて、腰のあたりに震えがくる。硬く勃ち上がったザックスのそこからも、ぬるぬると液体が溢れ出す。
「ザックス……頼む」
「ん」
もっと触れて欲しい。もっと振り回されたい。普段ならおよそ感じることのない感覚が、ザックスとこうしている時だけは不思議と沸き上がる。そして、それを素直に口に出してしまう自分に気がついたのは、いつ頃だっただろうか。
足の間に割って入り、付け根辺りをするりと撫で上げられる。自然と立てた膝を優しく掴まれたかと思うと、それと同時にぞわりと寒気が駆け上がる。
「ん……っ、っく」
じゅる、と音を立てた先。足指の先に力がこもり、無意識に閉じようとする膝を強く掴まれた。
「ちから、ぬいて」
触れるよ、と小さく呟いたザックスが、俺の頷きに気が付いたかはわからない。いちいち聞いて来なくたって好きに触れてくれればいいものを、毎回馬鹿丁寧に確認するのはわざとだろうか。却ってそれが俺自身の羞恥心を煽っていることに、気がついていないんだろうか。
「う……」
「クラウド、ここ、とろとろだ」
「う、るさ……い、あっ」
自分自身から伝い漏れた体液とザックスの唾液が混ざって、一番触れられたくない場所に触れられる。何度経験しても慣れないのは、こうして一番最初に触 れられる瞬間だ。自然と体に力が入り、声が出る。うわずった自分の声に対する嫌悪感で唇を噛む度に、ザックスはそんな俺を宥めて笑う。
「あったかい、中」
「だから、言うな、そういうこと……あ、あっ」
喉の奥で殺したように笑い、それからぐい、と奥まで指が入ってくる。力を抜けと言われたって上手くできるはずもなく、臍のあたりを何度も撫で上げられながら、ぐちぐちと奥をいじられる感覚。 増えた指の苦しさに身を捩る。 下腹部を手のひらで抑えられながら体の内側を、開かれる。
「クラウド、もう、いい?」
噛んだ唇を指でふわっとめくり、口腔内に入ってきた指先に、夢中でしゃぶりつく。挿れたい、と呟いたザックスに対する返事をどう返そうか。じっくり悩める程の余裕は、まるでない。
いつもいつも、ほんの少しだけ見せてくるザックスの底にある本能に、仕返ししてやりたいと思っている。だけど、毎回そんなことはできないまま終わる。 それでも、何も考えられなくなる事が実は嬉しくて、それが俺にとってどれだけ安寧の時間なのか。こいつはきっと、まだ知らないだろう。
――だからこそ、あんなものを渡したくなかったんだ。
「クラウド、入れていい?」
「ああ……っあ、うあぁっ!」
十分にほぐされた部分に、とろりと先走りで滑るザックス自身が突き入った。びくりとはねた体を両手で押さえつけられ、立てた膝が震える。はぁ、と深く息を吐いたザックスに見下ろされた瞬間、なんともいえない快感が全身を駆け抜けた。
「クラウド、中、すげえあったかい」
「あ、あ……っ」
やれと言われずとも、ザックスを締め付ける。 数度中をゆっくりとこじ開けられ、強く目を閉じる。
「なあ、クラウド、ちょっとこのままでも大丈夫?」
「なん……」
繋がったまま抱き起こされる。ひくひくと締まるそこから意識が離れないまま、向かい合う。体の中で主張し続けるザックス自身の熱を感じながら、何とか息を整える。ぐい、と体を引き寄せられ、ザックスの太ももの上に跨った状態のまま目と目を合わせ、キスをひとつ。乱れた髪を撫でつけるザックスが、とんとんと赤子をあやすように背中を叩く。
「なあ、クラウド。なんで普通に渡してくれなかったの」
「……」
撫でられた後頭部が、温かい。
「びっくりしたじゃない。慌てて隠すからさ」
「それ、は……っう、あ」
穏やかで優しい声だ。決して俺に対して怒りを抱いているわけではない。それでも、俺に対して向ける疑問への回答を欲したその言葉に返答しようとして、 一瞬声がうわずってしまう。
俺がザックスへとチョコを素直に渡せなかった理由。 渡したくなかった、理由。
――話せば、笑って流される程度だなんて、最初からわかっていたのに。
「ちょっと動くぜ……よっ」
「う、うぅ……っ」
話そうとはするけれど、自分の胎の中をじくじくと苛み続けるそれに振り回されてうまく言葉を吐き出せない。ゆっくりでいいから聞かせてくれと言われたって、こんな状態じゃあ、まともに伝えられやしない。
「……抜く?」
「嫌だ」
「即答じゃん」
笑いと共にザックスから吐息が漏れた。
渡したくない理由。 渡せないと思った理由。
「……渡したところで、到底、足りないと思っていたから、だ」
「足りない?」
ザックスが今俺の目の前にいることは、どれほどの奇跡だろう。大切なことを忘れ、思い出をどこかで落とし、ようやく目の前に現れたザックス自身に対してすら懐疑の目を向けていた。それでも笑って俺の腕を掴んでくれたザックスと、いつか約束した通りなんでも屋を生業に出来たこの事実。
「そんなのじゃ、全然……俺の、あんたへの感情は、そんなに、軽くない……っ!」
俺はザックスにとんでもないものをもらった。
それは例えば、自分の命。自分の力。回り回って自分の大切な人たちを守れるようになった、自分自身。大袈裟だって笑われるかもしれないけれど、俺自身はそう、認識している。
汗で滑る肌に指先が柔く食い込んだ。同時に突き上げられて、声が引き攣る。続きを促されなんとか口を開いても、思い通りの声が出ない。
「は、あ……っ、あぅ、ザックス、に」
「うん」
「こんなのひとつ渡しても……足りない、から」
「うん」
肩口にかけた手に力がこもる。
脱力した体を預け切っても、受け止めてもらえる安心感に目を閉じる。
「たくさんもらって、たくさん助けてくれて……っ、なのに、俺からはチョコひとつでは、全然……っ」
「クラウドぉ……!」
「っあ、あぁっ!」
黙って話を聞いていたはずのザックスが、急に俺を押し倒す。強引に抱え上げられた両足を折り曲げられ、腹のあたりにずしりと感じる重み。腹と太ももを これ以上ないほどに折り合わされて、最奥まで一気に突き上げられた。
「いっ、あ、ああっ……く、るし……」
「お前、おまえ、さあ……ほんっと……!」
あまりうまく伝えられなかった言葉をザックスがどう受け取ったか、全く理解できなかった。ただ突然抱き上げられたかと思えば、すぐにまたこうして押し倒され、こちらの意思確認を取らないまま性急に追い上げられる。一番つらい部分を的確に追い詰め、何度も突き上げられる。ぐちぐちと漏れる水音と、肌 のぶつかる音。うっすら目を開ければ視界の真上にはザックスの苦しげな顔があって、抱かれているのに抱いているような、不思議な気分になった。
「ザックス、あ、あっ、キツ……」
「お前ほんっと、そういうとこ、昔っから……変わんないのな」
「あ、う、うぅっ……な、にを」
「俺さあ、お前のそういうとこも、すっげえ、好き」
強く抱かれながら、それでも優しい声だった。その優しさに何度も助けられてきた自分から、何か返したかった。だけど、何を返せばいいかわからない。伝えたい事や渡したい物は沢山あったけれど、どれひとつとして自分自身を納得させられるものではなかった。 だから、素直に渡せなかった。
「は、あぁっ」
「あ、やばい、すげぇキツ……」
ザックスの動きが激しくなる。肩にかけた手に力がこもる。自分の体の内側を遠慮もなく激しくかき回され、宙に浮いた言葉とザックスの吐息で、頭がおかしくなりそうだ。
「クラウド……、なあ、クラウド」
余裕のなさそうな声。
「納得行かないならさ、じゃあ……もっと、くれよ」
「あ、ああっ」
途切れ途切れの意識で、精一杯その言葉を聞き取りたかった。 ザックスがぽつぽつと落とす声を聞き漏らしたくなかった。痛いほど硬くなった自分自身にそっと手を添えられ、追い上げられる。ぱちぱちと肌の当たる音。俺とザックスの体液が混ざり合って溶け合って、白いシーツに染み込んで行く。
「一回じゃ足りないなら、何度だってさぁ」
返答を諦めた俺の耳にただ流れ込む音と、声と、それからザックスの温かい手にされるがまま必死で首を縦に振る。
「一度じゃなくて、数で来いよ……全部受け取るから」
「ふ、あぁ、う……ん……!」
「俺だってさ、今年限りで終わらせてもらうつもりはないぜ」
吐息まじりに笑う声。追い詰められて、鼻先から抜け出るような声が出る。抱きつかれた背中に爪を立てて、逃げられないよう引き寄せる。激しく腰を打ち付けるザックスに向かって、言葉にできないセリフを何度も心の中で反芻する。
言ったな。ならその言葉通り、全部受け止めてくれ。
俺だって同じ気持ちだ。
このまま出せ。俺の中に全部出せ。
あんたがそれを望んでくれるなら、俺は喜んで受け入れてやる。
来年、再来年、そんな短い時間で満足できるわけがないんだ。あんただってそうだろう? いつか終わりがあるのだとしたら、その寸前まで。
「クラウド、俺もうだめ……っ」
「う、ん……」
両腕と両足で、その体を強く引き寄せる。びくびくと震えたザックス自身が俺の胎の中に思い切り吐き出した。
「は、っうぅ……はー、あっちぃ……」
数秒静止したザックスが一仕事終えたような顔で、俺の体の上にのしかかる。深く息を一つ吐き、するすると脇腹を撫で上げられた。
「……ザックス、ザックス、おい」
「んー……?」
これ以上ないほどとろけた顔でだらしなく笑いながら、火照ったままの肌に触れられる。うまく同時に達せなかった自分自身から、早く熱を吐き出したい。 触れられたい。自分がザックスの手で振り乱されて真っ白になる瞬間が、欲しい。
ん、と軽く頷いたザックスが、ゆっくりと体を起こす。吐き出されたばかりのそこにある白濁を掻き回すようにして、また動き始める。
どこから出ているのか判別がつかない甘い声。
馬鹿馬鹿しいとも思うけれど、これはきっと、チョコのそれより甘い時間だった。
Side Zack
だるそうにベッドへと体を投げ出したクラウドに、そっとタオルをかける。くったりと目を閉じ、うつ伏せで動かない体の邪魔にならないように立ち上がる。ベッドの縁へと追いやったチョコの箱は、気づけば最後の一粒だけになっていた。
「考えすぎなんだよ、お前は」
気持ちはそりゃあ嬉しい。俺だって、自分自身が今こうしてクラウドと一緒に過ごせている事に感謝しない日はない。だけど、それは何かを返して欲しいからじゃない。体だけが欲しいわけでもない。何もなくたって、俺自身がただクラウドとこれからもずっと一緒にいたいだけだ。
「なあ、クラウド」
返事はない。すう、と消えいりそうな寝息だけが、返ってくる。
「なーんもいらないんだぜ。ずっとそばにいてくれれば、それで」
案外、面と向かって言った事のない言葉だと思う。今だって多分、聞かれていないはずだ。
箱に残る最後の一粒をつまみあげ、ココアパウダーがこぼれ落ちないようにそっと舌先で受け止める。口の中に広がる甘い甘い感触に、一つ、鼻で息をする。すっかり空になった箱のパッケージを眺めようとそこに敷かれている蓋を取り外した瞬間、はらりと何かが足元に落ちた。
「……?」
拾い上げれば、白くて小さな封筒。糊付けもされていないその中を覗くと、メッセージカードまで入っていた。ちらりとクラウドの方を見る。まだ起きる気配は、なさそうだ。
「なんか書いてんのか……な、と」
仕事で常用しているであろうボールペンで走り書きされた文字が並ぶ。読み上げた瞬間、隣で寝こけるクラウドに今すぐ抱きつきたくて、仕方がなくなった。
「……ほんっと、お前ってさ」
――ここまで用意して、こんな事を書いて。
ここまで俺のことを想ってくれているのに、普通に渡してはくれない相棒。恋人と呼ぶにはあまりにも不器用で、友達と呼ぶには近すぎる。だけど、他の誰でも代替は効かない、ありえない。同じことを同じように思っていられるなら、それで俺はもう、十分だ。
ただひたすら、この関係がずっと続けばいい。今は、そう思う。
「……ごっそさんクラウド。愛してるぜ」
穏やかに寝息を立てるクラウドの髪をそっと撫でて、シャワー室へと目を向ける。クラウドが起きたら花を渡して、それからチョコでも買いに行こう。
まだ食べるのかって笑われるかもしれないけれど、俺からだって、渡したい。
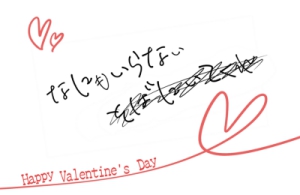
fin
2021.2.20、TM18にて頒布したものです。
手に取ってくださった方々、ありがとうございました!